
大学・企業が有する技術および研究人材の
付加価値を増大するプラットフォーム誕生
クリーク・アンド・リバー社(C&R社)が、設立から27年の間にネットワークしてきた 各分野のプロフェッショナルの叡智と、大学、企業などの優れた技術・研究を連携させることで、国内のオープンイノベーションの発展に貢献するオープンイノベーションプロデュース事業(OIP事業)」をスタートさせた。本記事では、「人間機械協奏技術コンソーシアム」研究戦略委員長の河口信夫氏(名古屋大学教授)に、同コンソーシアムの活動内容とOIP事業への期待をお聞きした。
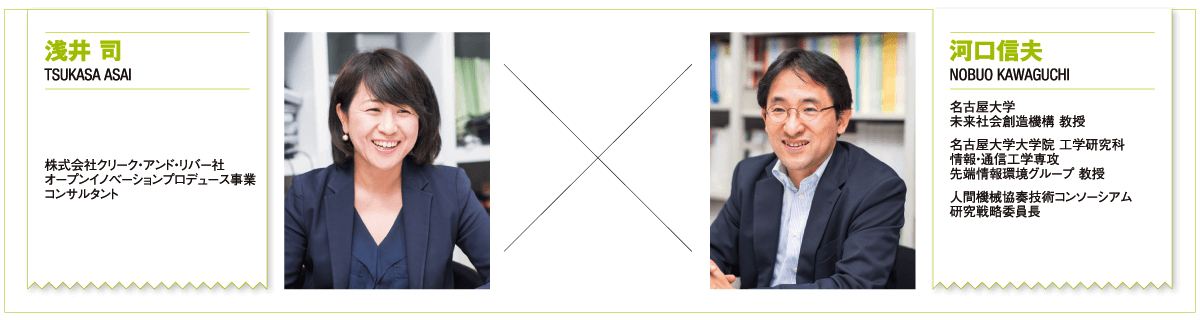
大規模共同研究の基盤をつくる
浅井
先生の研究生活は、ずっと名古屋大学一筋でいらっしゃるんですね。
河口
そうです。学生時代からすると、かれこれ30年近くになりますね。ただ、大学の中ではちょくちょく所属が変わっていますし、自分でベンチャー企業を立ち上げて外部の方と仕事したりしていますので、〝象牙の塔〟に引きこもって研究ばかりしているというタイプではありませんよ(笑)。
博士課程までは、バグのないコンピュータのソフトウェアをいかにつくるかという情報基礎論をテーマにしていたのですが、その後、興味のあった小型のデバイスを活用したモバイルコンピューティングといった方向にシフトしました。例えば、スマートフォン向けの時刻表カウントダウンアプリを開発し、200万人を超えるユーザーを獲得したり、スマホのセンサーを活用して人間の活動を理解しようというヒューマンアクティビティ・センシングに取り組んだり、あるいは「時空間ビッグデータ」と呼んでいるのですが、人という移動物を〝管理〟するために地下街商店街のマーケティングをやったり。いずれにしても、ただ論文のためではなく、世の中に役立たなければ意味がないというスタンスで、研究を行っています。
浅井
名古屋大が幹事になって推進している「人間機械協奏技術(HMHS)コンソーシアム」とは、どんなものなのですか?
河口
国の科学技術振興機構(JST)の「2017年度新規研究領域・共創コンソーシアム」に採択され、昨年末にキックオフしました。JSTサイドの狙いは大きく二つあって、そもそも国内の産学共同研究には、規模の大きなものが多くないんですね。企業から本気度の高い依頼が届いていないし、大学にも十分それに応える体制があるかといえば、心許ない現実がある。その状況を克服するために、まずは国の支援するプロジェクトを立ち上げて、お互い信頼し合って連携できる基盤づくりにつなげていこうというのが一つ。
二つ目に、共同研究というと、従来はほかからは見えないようにしてやるのが一般的でした。しかし、それでは、もしかしたらほかでも使える研究成果が、そこで閉じられてしまう。そうではなくて、知恵の部分はオープンにして大学に集積させ、それをいろんな企業が活用する、というスキームを確立しようという目論見があります。仮に各社が1000万円ずつ出資して集まれば、大学には億円単位の研究費を集めることも可能になるでしょう。そうすれば、企業が活用できる〝知〟も、さらに深く大きくできるわけです。
そういう大枠の中で、我々が始めたのが「人と機械との協奏システム」の追求です。機械がどんどん賢くなっていく未来に、人と機械はどんな関係を築くべきなのか、それをどう評価していったらいいのか、といったテーマに解を見出すコンソーシアムをつくろうというのが目的なんですよ。
浅井
名古屋大のほか、早稲田大学、東京工業大学、産業技術総合研究所が参加していますね。
河口
人間機械協奏を共通のテーマとして、我々は自動機械と人にかかわる技術、早大はセンシング基盤、東工大はセキュリティ基盤、産総研はサービス工学、といった観点を中心に企業との共同研究開発を進めています。
浅井
名古屋大の取り組みについて、簡単に教えてください。
河口
我々は、JSTのセンターオブイノベーション(COI)プロジェクトとして長崎大学、産総研と共同で自動運転技術の開発に取り組み、「オートウェア」というソフトウェアを作成して、オープンソース化しました。HMHSコンソーシアムでやるのはその先の話で、例えば「自動運転ができた時にはどんなユーザーインターフェイスが必要なのか?」「機械をどうコントロールしていくのがいいのか?」といった研究開発を行っていきます。自動機械と人や社会とのハーモナイゼーションを実現する「ハーモウェア」というソフトウェア群をつくって、それを共通基盤にしていこうという構想を持っているんですよ。
同時に、そうした研究開発を進めながら、優れた人材の育成、教育にも注力します。一つは、日本学術振興会の「リーディング大学院」(博士課程教育リーディングプログラム)制度の活用です。ここには、最初から修士、博士課程を5年間学ぶという前提で入ってもらう。そして、それなりのコストもかけて教育します。修士の時から毎年のように海外に留学させますし、ミーティングは全部英語。一線級の研究者を呼んだ講習会も頻繁に開くんですよ。
浅井
先日、そのプログラムを学ばれている方々の発表をお聞きしましたが、みなさん〝優秀〟の一言では片づけられない能力の高さで、感動すら覚えました。とかく企業側が口にする「うちで直接育てるから、博士課程の3年間はいらない」という発想は、あの学生さんたちを見ると出てこないはず。
河口
そういう認識が、徐々に広がってくれればいいのですが。
マッチングを阻む現実
浅井
ところで先生と弊社との関係は、当社の人間がいきなり「お話がしたい」と電話をかけたのが始まりでした。
河口
そうでしたね。私は情報処理学会の理事もやっているのですが、そこで企業向けの取り組みを強化しようという話が持ち上がったのです。「研究マッチング」ということで、要するに「こういうテーマで研究したいけれども、誰とやったらいいかわからない」という企業に適切な研究者を紹介するという、まさにC&R社さんがやられているようなことを模索していたわけですよ。ちょうどそのタイミングで連絡いただいたので、何か連携できないかという話がスタートしたのです。
浅井
あえて「研究マッチング」を意識されたということは、やはりそこがうまくいっていないという現実があるわけですね。
河口
そもそも論をいえば、企業が大学にあまり期待していないというのが実情だと思います。誤解を恐れずに申し上げれば、産学連携といっても、いい学生を送ってもらうためにお付き合い程度にやるというようなパターンが多い。だからまとまった資金が集まるはずもなく、目立った成果もなかなか上げることができないわけです。
そうした悪循環の原因は、もちろん大学側にもあるでしょう。ただ、企業のほうも大学に期待するものがズレている面は否めないというのが、私の率直な感想です。大学にも解きやすい課題とそうでないものがあるんですね。それがなかなか企業の方にはわかってもらえない。お互いに〝いい課題〟を選定することができれば、産学連携は大きな価値を生むと思うのだけれど。
そういう問題意識、具体的な課題を持つ人は、企業の中にもいるはずなのです。ところが、なかなかそういう人とつながることができないのも、大きな問題なんですね。
浅井
重要な指摘だと思います。私たちも、「誰と話をするか」というのが、営業の成否を分けますから。
河口
産学連携を成功させるとしたら、なにかデシジョンメーキングの判断の時点から大学と組んでやるというアプローチが、けっこう大事なのではないか、と私は思うんですよ。企業だけでは限界のある戦略的な研究方針の策定などに、大学の専門知を取り入れるわけです。ところが現実には、大半が「現場で困っていることを大学の助けを借りてどうにかしよう」というレベルの話になっている。そうした研究に価値がないとはいいませんけど、そればかりになっているのはやっぱり問題ではないでしょうか。
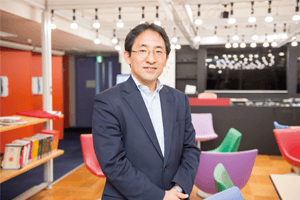
かわぐち・のぶお/1995年、名古屋大学工学研究科博士課程(後期課程)満了。名古屋大学工学研究科助手、講師、助教授を経て、2009年より、名古屋大学大学院工学研究科教授(情報・通信工学専攻)。ユビキタスコミュニケーションシステム、情報システム、通信ネットワークを専門に、幅広く活動している。大学発ベンチャー・株式会社ティアフォーの取締役でもある
※本文中敬称略
– ②へ続く-
コメント